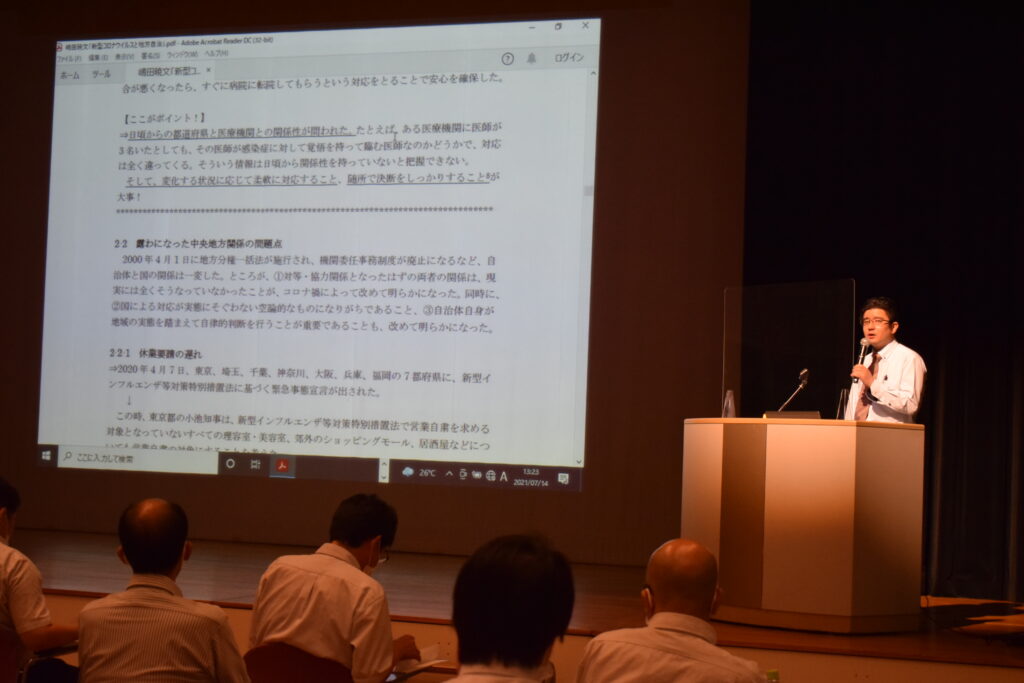現在、高度成長期に集中的に整備された公共施設・インフラが老朽化して一斉に更新時期を迎えつつある中、これらを現状のまま維持し続けることは困難であることが懸念されており、各自治体において「公共施設等総合管理計画」「個別施設計画」等に基づき公共施設マネジメントの取組が進められていますが、具体的な再編手法、コスト管理、人員の不足、組織内での意識統一、住民との合意形成等の様々な難しい課題に直面しています。また、今般のコロナ禍により、財政の更なる悪化、公共施設の在り方が問い直される状況等、公共施設マネジメントを取り巻く環境は益々厳しいものとなっています。
このたび、公共施設マネジメントの重要性を改めて認識し、課題の解決や実効性のある取組へのヒントを得ることを目的として、下記のとおり講演セミナーを開催いたしますのでぜひともご参加ください。
1 開催日時 2021年11月5日(金) 14:30~16:30
2 開催場所 三重地方自治労働文化センター 4階大会議室
3 講座内容 演題:ポストコロナで求められる公共施設マネジメントの進め方
講師:名古屋大学 大学院環境学研究科 教授 小松 尚 氏
4 参加対象 三重県地方自治研究センター団体会員及び個人会員、三重県内自治体の職員・議員等
5 参加費用 無料
6 申込方法 参加申込書に必要事項をご記入の上、FAX又はE-mailでお申し込みください。
7 申込期限 2021年10月26日(火)まで
8 主 催 三重県地方自治研究センター
電話 059-227-3298 / FAX 059-227-3116 / Eメール info@mie-jichiken.jp
※今後の新型コロナウイルス感染症の状況により、開催方法を変更させていただく可能性があります。
(Web会議ツールZoomを使用したオンラインによる講義等)
申込書 チラシ のダウンロードはこちらからお願いします↓